※ 本ブログは、米国時間 10 月 17 日 に公開された ”Ideas from the heart could help make employment more attainable for people with disabilities” の抄訳です。
キム チャールソン (Kim Charlson) 氏が緑内障で視力を失い始めたのは、彼女がまだ 11 歳の時でした。1 年半後に手術を受けたものの症状が改善することはなく、合併症によって失明の時期が早まる結果となってしまいました。
チャールソン氏の育ての親は、彼女に点字を学ぶよう勧めました。点字は、全盲や弱視の人が識字能力を高める鍵となります。その能力がなければ、チャールソン氏は大学に行くこともキャリアを築くこともできなかったでしょう。米国では、点字ができる視覚障碍者の学生はわずか 13% で、全盲または弱視の成人のうち約 70% が失業中です。
こうした残念な統計もあることから、チャールソンさんはあるアプリの登場に興奮しています。そのアプリとは、ObjectiveEd という企業が開発している点字 AI チューターアプリで、点字の学習と練習に費やす時間を増やすことができるというものです。同社はこのほど、マイクロソフトから AI for Accessibility の助成金を授与することになりました。この助成金は、AI を駆使したテクノロジにより、誰もが受け入れられる世界を作ろうとしている人に提供するものです。全国障碍者啓蒙月間に伴い、ロンドン大学シティ校、inABLE、iMerciv、オープン大学など、他にも 10 団体が同プログラムで助成金を受け取りました。
「障碍のある人に対してテクノロジをよりスマートで便利なものにすることは、マイクロソフトにとっての大きな機会であり、責任でもあります」と、マイクロソフトのアクセシビリティ担当シニアアーキテクトリードであるメアリー ベラード (Mary Bellard) は語ります。AI for Accessibility は 2018 年に開始し、これまでに 32 団体が助成金を受け取りました。その目的は、「AI、アクセシビリティ、そして障碍が交わるところで真に役立つものを構築する」人々を支援することです。
点字 AI チューターアプリは、ObjectiveEd のプレジデントであるマーティー シュルツ (Marty Schultz) 氏の最新プロジェクトです。シュルツ氏は、長年ソフトウェア開発者として、そしてボランティア教師として活躍しており、5 年前には目の見えない子どもたちに向け「目隠しレーサー」という iPhone ゲームを開発しました。その後、iPhone および iPad 向けに 80 種以上のゲームを提供することになり、ダウンロードの回数は 50 万回以上にのぼっています。
「もし 1 週間に 1 時間しか先生と一緒にいられないとしたらどうでしょう。1 週間に 1 時間しか指導を受けなかったとしたら、一体どれだけの子どもが活字を読めるようになるか考えてみてください」
チャールソン氏は、米国視覚障碍者協議会の元プレジデントで、シュルツ氏の作品の大ファンです。同じく、視覚障碍者および身体障碍者のための国立図書館サービスで消費者関係担当役員を務めるジュディ ディクソン (Judy Dixon) 氏もシュルツ氏のファン。2 人は、点字教育で識字能力を高めることや雇用の重要性について、シュルツ氏と頻繁に語り合ってきました。シュルツ氏は 2 人の意見を心に留め、構想へと進めていったのです。
全盲や弱視の児童の中にも、一部は自分のニーズに合った学校に通い、日々点字を学び使っている人はいます。しかし、多くは公立学校に通っており、週に一度学校を訪れる教師と約 1 時間を共に過ごす中で点字を学んでいるのが現状です。

「もし 1 週間に 1 時間しか先生と一緒にいられないとしたらどうでしょう。1 週間に 1 時間しか指導を受けなかったとしたら、一体どれだけの子どもが活字を読めるようになるか考えてみてください」と、チャールソン氏は語ります。「それだけでは不十分なのです。発育段階で状況に没入する必要があります。そうしないと、大人になっても十分な流暢さを習得することはできません」
点字 AI チューターアプリには、マイクロソフトの Azure Speech API を活用した AI ベースの音声認識機能が組み込まれており、パーソナライズされたゲーム学習計画で点字を読む練習ができるようになっています。アプリでは、点字を読む際に使われるハードウェアの一種であるリフレッシュ可能な点字ディスプレイに単語や文章が送信され、児童が点字を読み取って文字や文章を声に出して読みます。するとアプリはその音声を処理し、正しく読み取れているかどうかその場で答え合わせをしてくれます。
結果はウェブのダッシュボードに送信されるため、教師が児童の進捗状況を確認できます。
「私たちの役割は、児童に教えることではありません。教師がいなくても練習できるようにすることです」とシュルツ氏は語ります。「教師の役割は教えることですが、私たちは練習を楽しく魅力的なものにし、教師がいなくてもできるようにする役割を担っているのです。こうすることで、児童が次に教師と会う時にはかなり進歩していることになります」
こうして練習時間を増やすことで、「学校の成績も加速的に上がり、大学にも行けるようになります。また将来的には、より良い雇用機会にもつながります」とシュルツ氏は述べています。
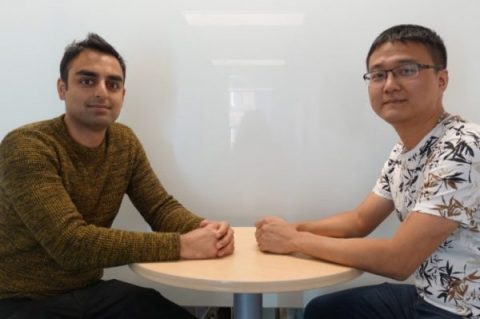
愛する人が視力を失っていく様子を見守ってきたビン リュー (Bin Liu) 氏とアルジュン マリ (Arjun Mali) 氏の 2 人は長年の友人同士。彼らは別の方法で視聴障碍者に手を差し伸べることにしました。テクノロジを使って、仕事に出かけたり街を歩いたりする際に役立ててもらおうと考えたのです。
リュー氏とマリ氏は、世界で全く異なる地域の出身ですが、似たような人生を歩んできました。中国で生まれたリュー氏は、土木技師の父親の仕事に伴い 9 歳で家族とともにボツワナのハボローネに移り住み、数年間その地で過ごしました。一方のマリ氏は、幼少期をインドとアラブ首長国連邦で過ごしました。父親が光ファイバーネットワークの営業担当者として両国で働いていたためです。
リュー氏の父親が手術不能の緑内障と診断されたのは約 10 年前のことでした。一方、インドにいるマリ氏の祖母は視野が一部欠けている状態でした。彼女は地元の盲学校で子どもたちに英語を読んで教えるボランティアをしていたので、マリ氏は時々彼女を盲学校に連れて行っていました。
リュー氏とマリ氏が出会ったのはトロントで、当時は 2 人とも大学生。ポーカーのプレイ仲間として仲良くなったのですが、2 人は全盲や弱視の人が直面する不満や侮辱、さらには視覚障碍者の活動範囲を改善する方法について頻繁に話し合っていました。
「祖母の弱視によって家族も影響を受けました。そこで、視覚障碍者コミュニティにインパクトを与えるような技術的ソリューションを生み出すことに機会があると考えたのです」と、オンタリオ州マクマスター大学で経済学の学位を取得したマリ氏は述べています。
リュー氏は、トロント大学で土木工学の学位を取得。父親が杖で障害物を正確に避けて歩けるようなデバイスがないか探したものの、見つからなかったと語ります。そこでリュー氏とマリ氏は共同で、最初の製品となる BuzzClip を開発しました。
BuzzClip は、クリップで装着する重さ 2 オンスのウェアラブルデバイスで、進行方向にある障害物を超音波で検知し、異なる種類の振動や周波数でユーザーに警告するというものです。
「祖母の弱視によって家族も影響を受けました。そこで、視覚障碍者コミュニティにインパクトを与えるような技術的ソリューションを生み出すことに機会があると考えたのです」
2 人は早期に、トロント大学でスタートアップテクノロジ企業を後押しするインパクトセンターからのサポートを受け、2014 年に iMerciv, Inc. を設立しました。
iMerciv は現在、AI for Accessibility 助成金の対象企業として、全盲や弱視の人に向けた歩行者ナビゲーションアプリ MapinHood を開発中です。このアプリは、職場や目的地まで歩く際のルートを選びたい場合も使えます。
MappinHood は、歩行中に避けるべき工事現場や犯罪の多い地域など、さまざまな危険を音声で警告します。また、噴水式水飲み器やベンチ、スロープなど、必要なものも知らせてくれます。こうした情報はすべて、機械学習やクラウドソーシングのデータ、地元警察からのオープンソース情報に基づいています。

現在のナビゲーションシステムは、一般的に目的地に到着するまでの最速ルートまたは最短ルートを出すようになっていますが、リュー氏は「例えば職場や店舗、公園への歩行ルートを探している障碍者にとって、最速ルートや最短ルートが最適とは限りません」と語ります。
MappinHood は現在、非営利団体であるカナダ国立視覚障碍者協会の支援を得てアルファバージョンとしてテスト中です。同協会は、BuzzClip でも iMerciv と協力しています。MappinHood は iMerciv のカスタムルートエンジンを使用していますが、AI for Accessibility 助成金を授与したこともあり、今後は Azure の機械学習やストレージ、仮想マシンも活用する予定です。
トロント版 MappinHood は、他の都市版アプリのテンプレートとしても活用できます。
「iMerciv ではパーソナライゼーションに注力しており、アプリを可能な限り柔軟にカスタマイズできるようにしたいと考えています」とリュー氏。「一般的に歩行者向けナビゲーションというものは、単一のソリューションですべてのニーズを満たすことはできません。障碍のある人であればなおさらです」

自閉症の人にとって、就職の最大の難関は面接です。そこに目をつけたのがニラジャン サルカー (Nilajan Sarkar) 氏。従兄弟の息子が自閉症だったのです。サルカー氏はのちに研究を進める中で、自閉症スペクトラムの人が、人間ではなくチャットボットのようなインテリジェントシステムにより良い反応を示すことがあると突き止めました。
サルカー氏は現在、テネシー州バンダービルト大学のロボットおよび自律システムラボにてディレクターを務めています。現在同氏が進めているのは、自閉症の人がインテリジェントシステムを使った就職面接で良い結果を出せるよう支援するプロジェクト。バンダービルト大学の自閉症と革新に向けたファーストセンターと共に、仮想現実でのキャリア面接準備 (CIRVR : Career Interview Readiness in Virtual Reality) を開発中で、今年になって AI for Accessibility プログラムに参加しています。
サルカー氏によると、米国における自閉症スペクトラムの成人は約 250 万人。「そのうち 60% 以上が何らかの仕事をすることが可能です。しかし、働ける人のうち 85% は、能力以下の仕事に就いているか失業者なのです」
「このシステムを活用して、実際に面接に行く準備をこれまで以上に整えてもらいたいと考えています」
CIRVR は、仮想現実の面接プラットフォームです。Azure AI を活用し、面接官としてコンピュータアバターを用意、面接者の心拍数や発汗といった生理的な数値を把握するウェアラブルデバイスを取り入れ、機械学習技術を駆使して面接者の不安を推測し、目線追跡機能で注意力を判別します。
「このシステムは、面接者の不安感や見ている場所、アイコンタクト、答え方、どうすべきだったのかなど、さまざまなデータを定量的かつ客観的に収集します。これでフィードバックシステムを作り出し、繰り返し練習することで面接スキルを向上させることが可能だと考えています」とサルカー氏は語ります。
「自閉症の人は時に、決められた形式で予測できる反応をするものとの対話を好む場合があります」とサルカー氏。「人間の反応や人間同士の対話は予測不可能で、混乱を招く可能性があるのです」
サルカー氏は、「対立を解決した事例について教えてもらえますか?」や「チームメイトをどのように支援しましたか?」といった自由回答形式の面接の質問は、多くの場合不安感を煽るとしています。また、プログラミングの問題を迅速に解決するといったような緊急性を求めるテストも不安につながるといいます。
サルカー氏によると、CIRVR のテストはすでに始まっており、面接の対応方法を改善できるよう、面接者にフィードバックを提供していく予定とのことです。これにより、面接官も必要に応じて面接の構成を変えることや、異なる質問をする方法を学ぶことができるとサルカー氏は述べています。
「面接の習慣構造が一晩で変わることはありません」とサルカー氏。「だからこそ、このシステムで実際に面接に行く準備をこれまで以上に整えてもらいたいのです」
AI for Accessibility で助成金を受けた組織はすべて「情熱にあふれており、アクセシビリティ関連のテクノロジに関する高い専門知識を持っています」と、マイクロソフトのベラードは述べています。
「ソフトウェアやハードウェアには、障碍のある人たちのニーズに応える可能性や、生活におけるテクノロジの役割に対するお客様の期待値を高める可能性があります。これは本当にすばらしい機会だと思います」
AI for Accessibility の詳しい情報 (英語) とマイクロソフト自閉症雇用プログラム (米国) の詳細はこちら(英語)。
—
本ページのすべての内容は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。正式な社内承認や各社との契約締結が必要な場合は、それまでは確定されるものではありません。また、様々な事由・背景により、一部または全部が変更、キャンセル、実現困難となる場合があります。予めご了承下さい。





